こんにちは!
いやおはようございます✨今朝の6時58分です。
動画で見たことをアウトプットしていきます!
MacBookのタイピングが楽しいw
🔁 習慣の鬼!この人の毎日のルールがすごい
- 毎朝6時に出社(自分との約束)
- どんなに夜遅くても、6時に会社に足を踏み入れる。
- 「意志力じゃなくて“ルール化”で動く」のがポイント。
- 日曜だけは少し緩める(7:30起き)
- 完全休みにはしないことで、リズムをキープ!
- 量が正義:商談・面談をとにかくやる
- 「質」を求める前に「量」をこなす。これが成長の近道。
- 夜のジャーナリングで気持ちを整理してから眠る
- 1日の振り返りが、自分を整える時間になっている。
- 筋トレ&サウナで体も心も整える
- 肉体から整えることで、メンタルのリズムも守っている。
💬 考え方の芯がブレない
- 「自分との約束を破るのは、自分に失礼」
- 他人よりまず自分との信頼関係。
- 量と質、両方に向き合う
- 量をやりながら質を上げていくスタイル。
- 「夢」は期限をつければ「目標」になる
- ふわっとした願望ではなく、行動に落とし込む。
- 批判されても発信する勇気
- SNSでの低評価やコメントも、「注目されている証拠」として捉えるメンタルがすごい。
- 環境に左右されず、自分の“仕組み”で動く
- 雨でも早朝でも関係なし。自分で自分の行動をデザイン。
✍️ じぶんにも活かせるポイントはここ!
- 朝の行動を「ルール化」してしまうことで、迷いなく動けるようにする
- 「今日はこれができた!」を夜に書くことで、1日を気持ちよく終える
- 発信(ブログやスタエフ)も、「反応がなくてもまず出す」ことで経験値を積む
- 自分にとっての「夢」や「目的」を、言葉で表しておくと行動に力が湧く
🎯 これからの具体的なアクション案(3つ)
- 朝活ルールを再設計してみる
- 例えば「5:00台に起きて“オートパイロット”を発動させる」と決める!
- 毎日の“できたこと”を1行で記録
- 日記アプリやメモ帳でもOK。夜の自分との対話時間をつくろう。
- 小さくても毎日発信する
- X(旧Twitter)やスタエフで「今日の学び・気づき」を毎日ポスト。
- 「注目されないと意味ない」じゃなく、「出すことが価値になる」と考える!
📝 最後に:動画を見て自分が感じたこと
「決めたことをやり続ける人って、かっこいいな」と思いました。
しかもそれが、ガチガチの修行ではなく、自分との“信頼関係”を築くためのものだと知って、すごく共感しました。
そして、「自分を変えたいなら、まずは“仕組み”を変えよう」という言葉が心に残りました。
次は二つ目の動画から学んだことです♪
科学的に証明された「すごい習慣」まとめと活用法
日々の生活や仕事をより良くしたいと願っても、「続かない」「疲れる」「結局やめてしまう」という経験は誰にでもあります。
今回は『科学的に証明された すごい習慣大百科』の内容から、特に実践しやすい習慣を整理しました。さらに、それを 日常生活や教育現場(小学校教員)でどう活かせるか を考えていきます。
🛁 体と心を整える8つの習慣
- 手を温める(手湯)
38℃のお湯に10〜15分手を浸すと、自律神経が整いリラックス効果。痛みの緩和や回復モチベーションにも。
👉 教員活用例:授業の合間や放課後に“手湯休憩”を取り入れる。手軽で短時間でも気分が切り替わる。
- 入浴(10分間)
脳波や心拍が落ち着き、睡眠の質や翌日の集中力がアップ。
👉 教員活用例:残業後にお風呂でリセット。夜に気持ちを切り替えることで翌朝スッキリ教室に立てる。
- 映画は映画館で観る
映画館鑑賞は軽い有酸素運動に相当し、集中力やストレス軽減に効果的。
👉 教員活用例:休みの日に映画館へ。リフレッシュしながら「集中しきる体験」を味わう。授業の集中力指導にもつなげられる。
- 縄跳び10分+水分補給
脂肪燃焼・心肺機能アップ・体力向上。さらに集中前に500mlの水を飲むと脳が活性化。
👉 教員活用例:朝活に軽く縄跳び→授業準備。子どもたちにも「勉強前の水分補給」を習慣化させると効果大。
- 食事前におでこをタッピング
30秒軽く叩くと食欲が1/2〜1/3に。ストレス食いの予防になる。
👉 教員活用例:給食前のリズム活動に軽いタッピングや体操を入れることで、自然に食欲を整えられる。
- 怒らず穏やかに
怒りは免疫を6時間以上低下させる。反対に思いやり行動は免疫力を41%上げる。
👉 教員活用例:クラス経営では「叱る」より「認める」。免疫だけでなく人間関係も健康的になる。
- ゆっくり動く・深呼吸
呼吸・血圧が整い、創造的思考を促す。忙しい時ほど効果あり。
👉 教員活用例:授業が騒がしくなったら「深呼吸タイム」を取り入れる。先生自身の落ち着きにも直結。
- スキップ・爪ケアなど外見の整え
姿勢や外見のケアが感情に作用。自尊心を高める。
👉 教員活用例:朝にネクタイをきちんと締める、爪を整える。子どもにとって「先生が整っている」という姿は安心感につながる。
🧠 続けるための仕組みづくり
- まず動く(小さく着手)
行動すると脳の「やる気スイッチ」が入る。
👉 宿題やプリント整理も「まず1枚やる」から始めてみる。 - 習慣にくっつける(習慣連結)
既存の行動に新しい習慣を接続すると継続しやすい。
👉 例:朝コーヒーを入れたら必ずジャーナリングを1行書く。 - 環境を変える(ナッジ)
行動を促すように環境を設計。
👉 教室でも「使う教材は黒板前に置く」「注意文を目につく場所に貼る」といった工夫ができる。
🌱 教師の日常・生活に落とし込むなら?
- 授業前:水を飲む+深呼吸
自分も子どもも集中力アップ。 - 学級経営:怒るより認める
免疫的にも心理的にもプラス。 - 放課後:手湯や散歩で気持ちを切り替える
家庭に帰る前に心を整えることで、家族時間も笑顔で過ごせる。 - 朝活:ジャーナリング+軽い運動
脳の“オートパイロット”を作動させる一日の始まりに。
✨まとめ
「科学的に証明された習慣」は、一見シンプルで地味ですが、積み重ねると確実に生活と仕事の質を高めてくれるものばかりです。
特に教師という仕事は、体力・集中力・人との関わりがフル稼働する職業。だからこそ、こうした小さな習慣を取り入れて、自分も子どもたちも笑顔で過ごせる環境をつくっていきたいですね。





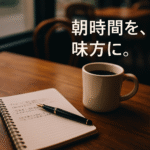
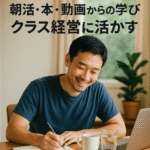
コメント